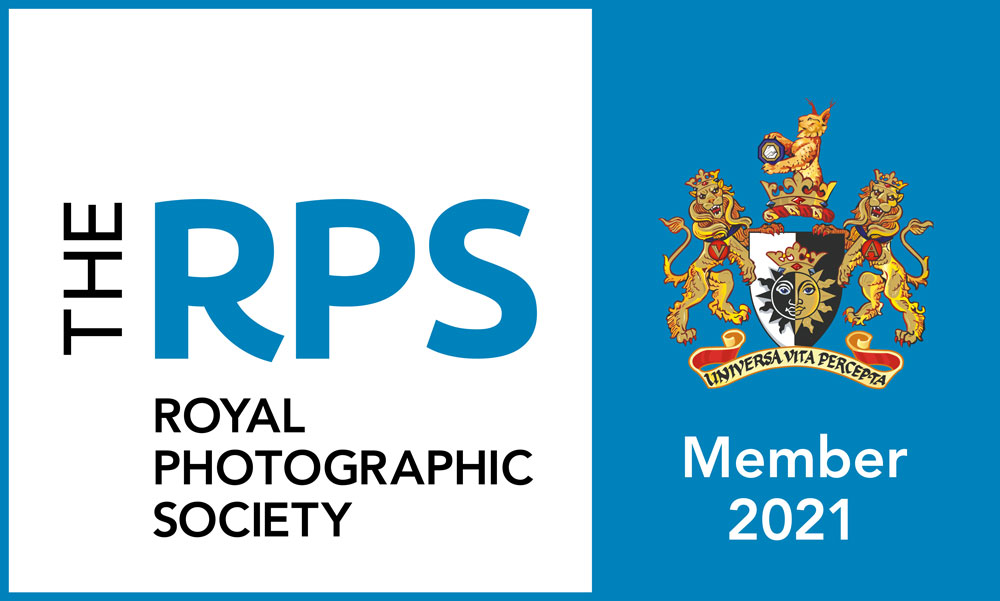日本初開催、世界遺産セント・キルダ 写真展
「ST KILDA」
そこは世界のはての島。
英国の最も西のはてに、『セント・キルダ』という絶海の孤島があります。群島全体がユネスコ世界遺産(自然遺産、文化遺産の両方)に登録されており、英国だけでなく世界的に大変貴重な保護遺産です。
この島は1930年、最後の島民36人が島を捨てスコットランド本土へ避難し無人島となりました。 そこに至った悲劇の物語は英国では広く知られていますが、日本ではあまり知られていません。 この度、大規模な写真展としては国内初となるセント・キルダの写真展を行います。 本展では写真家の加藤秀がセント・キルダ群島にて撮影した写真作品の中から、およそ20数点を富士フイルムイメージングプラザ東京、および大阪(巡回展)にて展示いたします。
写真展「ST KILDA」
東京展
2022. 3.16 WED - 4.4 MON
FUJIFILM Imaging Plaza 東京
大阪展
2022. 4.27 WED - 5.16 MON
FUJIFILM Imaging Plaza 大阪
時間: 10:00-18:00 (火曜休館)※東京・大阪とも
入場料: 無料
後援:
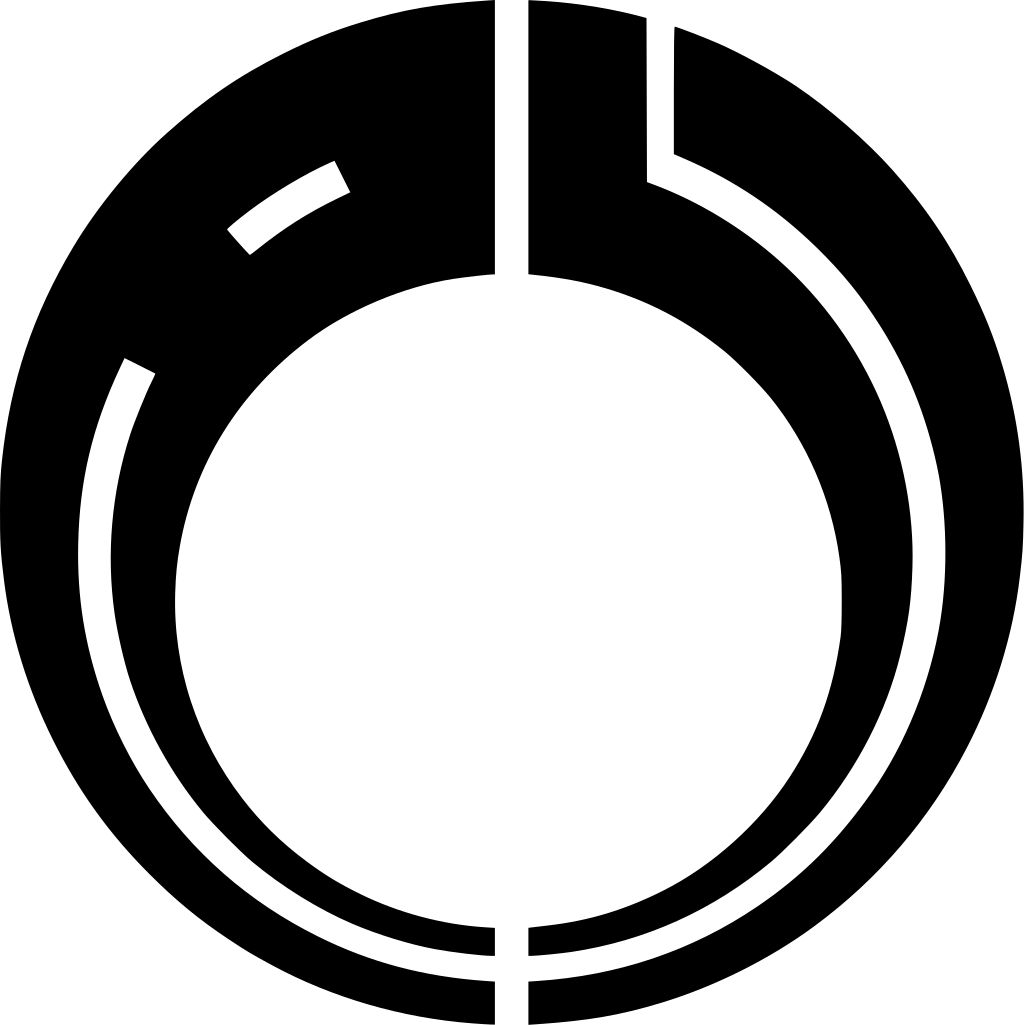 外務省
外務省  スコットランド国際開発庁
スコットランド国際開発庁



世界遺産「セント・キルダ」

世界のはての島
セント・キルダは英国西岸沖に連なるアウターヘブリディーズ諸島の中で最も西の果てに孤立する群島で、4つの小島と巨大な離れ岩(海食柱)で構成されています。 年中吹き荒ぶ暴風と荒波、そして海から高くそびえる断崖絶壁は人々が島に近づくことを長らく拒絶してきました。この島には嵐の吹き荒れる冬は勿論、夏ですら近づくことは容易ではありませんでした。 唯一の有人島だったヒルタ島は7㎢に満たない小さな島で、土地は痩せており、強風で木は1本も育たず、海は荒れ漁業も出来ませんでした。
古代からの自給自足の暮らし
だが、そんな過酷な自然環境にあっても、ここにはかつて人が暮らしていました。 少なくとも4,000年以上前からこの島に根づき自給自足の暮らしを行ってきました。 人々は危険な断崖で命がけで海鳥猟を行いこれを主食とし、羊や牛を育て、わずかな土地で大麦やじゃがいもを作りました。 毎朝、成人男子全員による議会が開催され、大事なことやその日やる事が皆で決められていました。 食糧や必要なものは平等に分配され、質素な暮らしながら誰もが互いに助け合い暮らしました。 電気も法も通貨も貧富の差もない、外界から遠く隔絶した小さな世界には心豊かな暮らしがあったのだといいます。

毎朝、集落のメインストリートに成人男性全員が集まり議会が開かれた。その日行うことや重要なことを皆で決めました。(1928年)
 観光客との写真撮影に応じる島民の女性たち(1913年)
観光客との写真撮影に応じる島民の女性たち(1913年)©︎A visitor from SS 'Hebrides' poses with two islanders, c1913
National Records of Scotland, GD1/713/1
変わりゆく時代
ところが18世紀の産業革命以降、特に19世紀に新型蒸気船が登場すると、本土から多くの人が訪れるようになります。 知られざる未開の島であるセント・キルダはロマンティックなイメージで本土の新聞に報じられました。 富裕層による観光ツアーが企画され、ツアー会社はPR映画まで作られました。 資源に乏しく気候の影響を受けやすいセント・キルダが食糧危機に陥ると、「セント・キルダを救え」の旗印に食糧が届けられ、"世界の果てに生きる貧しい人々"を見物しようと観光客は島へ押し寄せました。 島の人々は、観光船が訪れると一番の服装でおめかしをして観光客を迎え、記念撮影にも喜んで応じました。
長らく質素に暮らしてきた島へは、実に様々なものが持ち込まれるようになりました。 開かれた世界、新しい価値観、だが厄介なものも持たらされた。それは感染症でした。 島民は感染症に対して免疫が乏しく、風邪やインフルエンザも重症化し次々と命を落としました。 特に1727年夏には天然痘が猛威を震いました。94人(島民の約90%)が死亡し島は壊滅的となりました。 また破傷風による新生児の致死率は80%にまで達するなど深刻さを極めました。
第一次世界大戦中、島には海軍が駐留し定期的に物資が届けられました。 だが大戦が終わると軍は退去し補給もなくなりました。支援は途絶え、再び島は食糧危機に直面します。 若者はより良い生活を求めて次第に島を離れ、残ったものは疫病に倒れました。 本土の人々が行ってきた食糧などの善意の支援は、結果的に島民たちの自活力を失くしてしまい、かつての自給自足の日々にはもう戻れなくなってしまっていました。 そして島での暮らしは限界を迎えます。 1929年の冬は特に厳しい冬で数名が亡くなり、翌1930年5月の若いメアリー・ギリーズの死は島民の離島の意思を決定づけるものとなりました。
全島避難
本土への移住支援をしたためた請願書が全成人の署名により作成され、これが政府に受け入れられます。 1930年8月、軍艦ヘアベル号にて36人の全島民は涙ながらに島を後にしました。 誰もが皆、生まれ育った愛しい故郷を離れたくはありませんでした。 かくしてセント・キルダは無人島となり、かつての住まいは崩れ落ち廃墟となりました。 使われなくなった煙突はフルマカモメの巣になり、人のいなくなったセント・キルダは野生動物たちの楽園となりました。

セント・キルダは世界最大級のシロカツオドリのコロニーとなっています。営巣し春から夏の産卵期をこの島で過ごします。

かつてこの家に暮らした人の名が軒先に残されています。
望郷の思いと共に
その後、1986年にセント・キルダはスコットランドで最初のユネスコ世界遺産に登録されました。 文化遺産と歴史遺産の両方に認定された英国唯一の複合遺産で、1,100を超える世界遺産の中でも複合遺産はわずか39しか登録されていません。 現在、セント・キルダにはレーダー施設の防衛担当者が通年駐在する他、島の環境保全に携わるスコットランド・ナショナル・トラストの職員と、学術研究グループなどが春から夏にかけて短期滞在するのみで住民はおらず定期船もありません。
ヘアベル号で島を去った島民たちは、本土でそれぞれの人生を歩むが、その後もたびたび島へ里帰りに訪れ、失われたかつての島の暮らしを懐かしんだといいます。 2016年4月、セント・キルダの最後の元島民レイチェル・ジョンソンが93歳の天寿を全うすると、元セント・キルダ島民はすべてこの世を去りました。
荒々しくも美しいセント・キルダには、かつての島民たちが残した暮らしの名残と共に、温かく懐かしい思い出と、もう手の届くことのない望郷の想いが満ちています。